
最近『Web3』って言葉をよく聞かない?なんか難しそうだけど、一体なんなんだろう…?

『Web3』、テレビやTwitterで話題になっていますよね。
未来のインターネットと言われていますが、まだ馴染みが薄い方も多いかと思います。
突然ですが、みなさんは「Web3」という言葉を聞いたことがありますか?
なんだか難しそう、怪しい、と思う人もいるかもしれません。
でも実は、Web3はこれからの私たちの生活を大きく変える可能性を秘めた新しいインターネットのカタチなんです。
この記事では、「Web3が何か」「なぜ注目されているのか」を、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
はじめに
みんなが抱えるインターネットの悩みとは?

SNSやネットショッピングって便利だけど、なんだか自分のデータが勝手に使われてそうで、ちょっと不安に感じる時ってない?
いま、私たちが使っているインターネットは「Web2.0」と呼ばれています。
TwitterやFacebook、Instagramなどが代表的ですね。
これらは非常に便利な一方で、私たちのデータはそれらのサービスを提供している企業に集約され、管理されています。

でもそれって、プライバシーは本当に守られているのかしら?
サービスが突然なくなったら、私のデータはどうなるの?
そんな疑問や不安を抱いたことはありませんか?
Web3は、まさにそうした現代のインターネットが抱える課題を解決するために生まれた技術なんです。
Web1.0、Web2.0、そしてWeb3.0へ!インターネットの進化を振り返ろう
Web1.0:読むだけのインターネット(~2000年代前半)
Web3について理解を深めるために、まずはこれまでのインターネットの歩みを簡単に振り返ってみましょう。
「インターネット」という言葉ができて間もない「Web1.0」の時代。
この時代のインターネットは、企業や個人が作ったウェブサイトを「読む」ことが中心でした。
このころから掲示板への書き込みなどはすでにありました。
ですが、基本的には情報の発信者が一方的に情報を提供し、利用者はそれを受け取るだけです。

Web1.0と呼ばれる社会では、今のように誰もが気軽に動画やブログを投稿するような時代ではありませんでした。
Web2.0:誰もが参加できるインターネット(~現在)
SNSやブログ、動画サイトの登場により、状況は一変します。
ユーザーは情報を「読む」だけでなく自ら「書く」、つまり発信する側にもなりました。
これが現在まで続くWeb2.0の世界です。
これにより世界中の人と簡単につながり、コミュニケーションをとることが可能になりました。
しかし、このWeb2.0には大きな課題があります。
それは、膨大なユーザーデータを少数の巨大IT企業(Google、Apple、Metaなど)が管理していることです。
便利さと引き換えに、私たちのデータやプライバシーは彼らの手に委ねられているのが現状です。
Web3.0が生まれた背景

Web2.0の便利さを享受する一方で、データの管理を特定の企業に依存するという課題が生まれました。
この課題を解決するために考案されたのが、Web3だとお考えください。
Web3は、この中央集権的な構造から脱却し、インターネットを本来の「みんなのもの」として取り戻すことを目指しています。
Web3を一言で言うと?

Web3を簡単に言うと、特定の会社に頼らずみんなで管理するインターネットのことです。
「管理者」がいない未来のインターネット
Web3を最もシンプルに表現するなら、「分散型(Decentralized)」という言葉がぴったりです。
これまでのインターネット(Web2)は、GoogleやTwitterのような特定の巨大企業が中心となって情報を管理していました。
例えば、Twitterに投稿したつぶやきは、Twitter社という「管理者」が持つサーバーに保存されます。
もしTwitterのサーバーに障害が起きたり、会社の方針でサービスが停止したりすれば、あなたのデータは閲覧できなくなってしまうかもしれません。
一方でWeb3では一つの管理者に頼らない、ネットワークに参加する世界中のユーザーが協力してデータを管理します。
この管理には、ブロックチェーンという技術が使われます。
つまり、データの所有権や管理権が特定の企業から、私たちユーザーそれぞれの手に戻ってくるのです。

なるほど。これまでのインターネットは、大きな会社が管理する『中央図書館』みたいなものなのね!
それに対してWeb3は、みんながそれぞれ記録していく『地域の共有図書館』みたいなイメージね!
この「管理者」がいないという仕組みが、Web3の最も重要な特徴であり、これまでのインターネットとの決定的な違いです。
Web3を支える3つの重要なキーワード

Web3が「管理者のいない自由なインターネット」なのはわかったけど、具体的にどんなことが出来るようになったのかしら。

Web3を理解するにあたって、まずおさえておきたい言葉が存在します。
Web3のきっかけとなった「ブロックチェーン」
それを利用した金融サービス「DeFi」
デジタルデータを唯一のものにする「NFT」
今回はこれらについて説明しますね。
ブロックチェーン:みんなで守る「公開された台帳」
ブロックチェーンは、Web3の土台となる技術です。
取引のデータが鎖(チェーン)のようにつながって記録されるため、「ブロックチェーン」と呼ばれます。
ブロックチェーン技術により、一度記録されたデータは改ざんが非常に困難になります。
なぜなら、ブロックチェーンはネットワークに参加する全員が同じ台帳を共有しているからです。
同じ台帳を共有するため、透明性が非常に高くなり、改ざんが非常に困難になるのです。

この仕組みなら誰かにデータを勝手に変えられたりしないし、履歴もみんなが見られるから安心して取引ができそうね!
これが、Web3が「管理者」を必要としない理由の一つです。
ブロックチェーンについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
DeFi(ディファイ):銀行を介さないお金のやりとり
ブロックチェーン技術を利用することで新しく生まれた金融サービスがDeFi(ディファイ)です。
DeFi(Decentralized Finance)とは、「分散型金融」のことです。
これまでの金融サービスは銀行や証券会社といった中央集権的な組織を介して行われていました。
しかし、DeFiはブロックチェーン技術を用いることで、仲介者を介する必要がなくなります。
その代わりに、個人間で直接金融取引を行うことを可能にしたのです。
NFT:世界にたった一つの「デジタル資産」
NFT(Non-Fungible Token)とは、「非代替性トークン」のことです。
ブロックチェーン上で発行され、デジタルデータに「唯一無二の証明書」を付与する技術です。
これまではデジタルアートや音楽などは簡単にコピーできてしまいました。
しかし、NFTにすることで誰が本物の所有者であるかを証明できるようになります。

デジタルデータに資産としての価値を与え、取引できるようにする技術だと考えていただければ分かりやすいでしょう。
NFTは、デジタルデータが資産として扱われるWeb3の世界を象徴する技術です。

「改ざんされないデータを作る」というブロックチェーン技術によって、Web3が成り立っているのね。
Web3で私たちが得られるメリットとデメリット

Web3は自由なインターネットを目指していますが、一概にいいことばかりではありません。
どの世界でも自由に責任はつきものです。

そういわれるとちょっと身構えちゃうけど、確かにその通りよね。
これからのためにもWeb3のメリットとデメリット、どちらも知っておきたいわ!
Web3のメリット

新しい技術には、必ず良い面と注意すべき面の両方があります。
Web3についても、その特徴をしっかり理解しておきましょう。
プライバシーの保護とデータ主権の回復
特定の企業があなたのデータを独占的に管理することがなくなります。
そのため、プライバシーがより強固に守られます。
自分のデータは自分で管理し、誰と共有するかを自分で決められるようになります。
中央集権からの脱却と検閲への耐性
分散型であるため、特定の企業や国によるサービス停止や情報検閲がされにくくなります。
これは、表現の自由を守ることにもつながります。
新しい経済圏の創造
NFTやDeFiといった技術により、データが資産になります。
ゲームのデータに価値がついたり、クリエイターが自身の作品を限定販売できたり、新しい価値が生まれる場が広がるでしょう。
Web3のデメリット

Web3は「自己責任」が前提となる世界です。
メリットを享受するためには、デメリットを理解し、注意深く利用することが何よりも重要になります。
技術の未熟さとセキュリティリスク
Web3はまだ発展途上の技術です。
法整備も不十分な点が多く、詐欺やハッキングといったセキュリティリスクがWeb2よりも高くなる可能性があります。
操作の複雑さ
Web3はWeb2に比べてユーザー自身が行うべき操作が多く、初心者には少し複雑に感じられるかもしれません。
ウォレット(デジタルのお財布)のパスワード管理はオンラインに保管しているとハッキングの恐れがあります。
革新的な技術ゆえに、サービスの日本への普及の低さから英語表記が多いのも、Web3の難しさです。
Web3は私たちの未来をどう変える?具体的な例を見てみよう

Web3がブロックチェーンの革新的技術革命なのも、メリットとデメリットもわかったわ。
でもそれで、私たちの生活って具体的にどう変わるのかしら?

Web3が普及すると、私たちのデジタルライフは今とは全く違う形になるかもしれません。
ここでは、その具体的な例をいくつかご紹介します。
未来のSNS:データが自分のものになる
現在のSNSでは、投稿した文章や写真はサービスを運営する企業のサーバーに保存されます。
しかしWeb3のSNSでは、あなたの投稿はブロックチェーン上に記録され、あなた自身が所有権を持ちます。
・投稿が資産になる
あなたの投稿やコンテンツがNFTのように資産価値を持ち、他のユーザーと直接売買できるようになるかもしれません。
・運営に左右されない
もしSNSの運営会社がサービスを終了しても、データはブロックチェーン上に残るため、自分の投稿が消えてしまう心配がありません。
・広告と報酬
広告を見ることで、ユーザーが報酬(トークン)を得られるような新しい仕組みも考えられます。
未来のゲーム:遊んで稼ぐ「Play to Earn」

ゲームの世界も大きく変わります。
これまでゲーム内で手に入れたアイテムは、あくまでそのゲームの中だけの価値でした。
Web3のゲーム(ブロックチェーンゲーム)では、ゲーム内のアイテムやキャラクターがNFTとして扱われます。
これにより、以下のようなことが可能になります。
・アイテムが自分の資産に
手に入れたレアアイテムやキャラクターを、ゲームの外のマーケットプレイスで他のユーザーに売却し、現実の利益を得ることができます。
・異なるゲーム間でのアイテム利用
将来的には、あるゲームで手に入れたアイテムを、別の対応するゲームでも使えるようになるかもしれません。
このように、Web3は単なる技術の進化だけでなく、クリエイターやユーザーへの「価値の還元」という、新しい経済の仕組みを生み出す可能性を秘めているのです。
まとめ:Web3は「新しい選択肢」
今回はWeb3について解説しました。
Web3は決して、今あるインターネット(Web2)を完全に否定するものではありません。

Web3は、これまでのインターネットが抱えていた課題を解決するための、新しい『選択肢』だと考えていただくと良いかもしれません。
特定の企業が提供する便利さを享受するWeb2と、個人の主権を重視するWeb3。
私たちは、用途や目的に応じて、それらを使い分けられる未来が訪れるでしょう。
まだWeb3の技術は発展途上であり、学ぶべきことも多くリスクも存在します。
しかし、私たちはインターネットが生まれてからずっと、より便利で、より安心できる未来を目指して進化を続けてきました。

最初は難しく感じるかもしれないけど、興味を持った分野から少しずつ調べてみるのもいいかも!
きっと新しい発見があるはず!
Web3は、これから私たちの生活に深く関わっていく可能性を秘めています。
まずは小さな一歩から、未来のインターネットを覗いてみてはいかがでしょうか。

最後まで読んでいただきありがとうございます。
今回の記事はここまでとなります。
もしよろしければ、ほかの記事も読んでいただけると今後の活動に大変励みになります。
読んでいただいた皆様、応援してくださる方々、いつも本当にありがとうございます。
それではまた、別の記事でお会いしましょう。


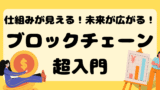


コメント