
ねぇ、AIって結局どう使えばいいのかしら?
話しかけても、なんだかピンとこない答えが返ってきちゃうのよね。

たしかに、最初は戸惑いますよね。でも、少しコツを掴めば、AIはあなたの期待に応えてくれるようになりますよ。
「AIってよく聞くけど、どう使えばいいの?」
「いざ使ってみても、なんか思った通りの答えが返ってこない…」
そんな風に感じていませんか?
Web3時代を生きる私たちにとって、AIはもはや身近な存在。
でも、その真価を引き出すにはちょっとしたコツがいるんです。
実は、AIが「勘違い」したり「的外れな回答」をしたりするのには理由があります。
それは、私たちがAIに「どう質問するか」が大きく関係しているから。
この記事ではAIへの指示文、つまり「プロンプト」の基本から、 あなたの「こうしたい!」をAIがしっかり理解してくれるようになる上達のコツまでやさしく解説していきます。
この記事を読めば、あなたもAIをまるで優秀なパートナーのように使いこなせるようになるはず。
さあ、一緒にAIとのスマートな対話を始めてみましょう!
AIとの対話、その前に!AIはどうやって質問に答えているの?

AI(大規模言語モデル)の基本的な仕組みとは
AI、特にChatGPTのような「大規模言語モデル」は、みなさんが想像するような人間のように考えているわけではありません。
実は、AIはインターネット上の膨大なテキストデータを学習して、次にくる可能性が最も高い単語の最小単位である「トークン」を予測しているだけなのです。
例えるなら、スマホの予測変換機能の世界規模版です。
あなたが「美味しい」と入力すると、スマホの予測変換や検索エンジンは「ご飯」や「お店」といった単語を候補として表示しますよね。
これと同じように、AIに「面白い小話を書いて」と指示すると、AIは学習した膨大なデータの中から「面白い小話」という指示によく続く文章のパターンを統計的に探し出し、最も自然に続くトークンを順番に生成していきます。
つまり、質問に「答える」というよりも、質問に続く最もらしい文章を「生成している」と理解すると、AIとの対話がよりスムーズになります。
AIが「勘違い」する理由と「ハルシネーション」の正体
AIが時々、事実とは異なる情報を提示することがあります。
これは「ハルシネーション(Hallucination)」と呼ばれ、多くの記事では「AIが嘘をつく」と表現されることが多いです。
しかし、実はAIは意図的に嘘をついているわけではありません。
AIの誤情報は、嘘ではなく「勘違い」や「指示の矛盾解消」であることが多いのです。
たとえば、情報が曖昧な質問に対して、AIは学習データから最もらしい情報を「勘違い」して提示してしまうことがあります。
また、人間が矛盾した指示を出した場合、その矛盾を解消しようとして、結果的に誤った情報を出力してしまうケースも少なくありません。
AIの得意・不得意を知ることが上達の第一歩
AIをうまく使いこなすためには、AIの得意なことと苦手なことを知ることが大切です。
AIは、文章の要約や翻訳、アイデアのブレインストーミングなど、大量のテキストを扱う作業は非常に得意です。
一方、まだ起きていない未来を予測したり、倫理的に難しい判断をしたりすることは苦手です。
例えば、タロット占いをAIに依頼しても、未来を予測することはできません。
しかし、質問の仕方を変えれば、AIは力を発揮してくれます。
このあと解説しますが、「プロのタロット占い師と同じプロセスでカードを選び、その結果選出されたカードの意味を教えてください」と聞くと、AIは「占い」という体裁を取りながら、学習データからカードの意味を的確に解説してくれるのです。
AIプロンプト作成の基本と上達のコツ
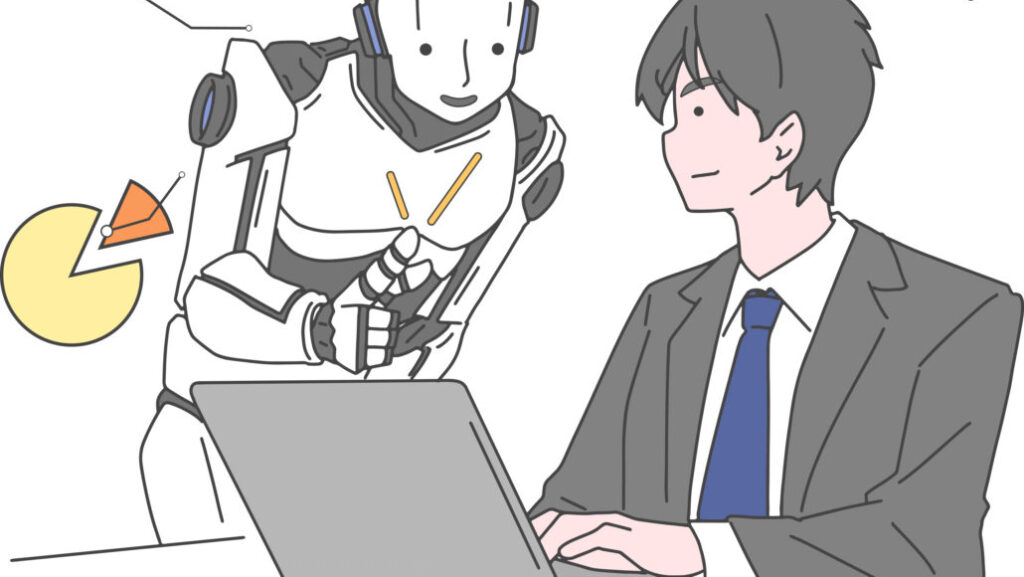
AIに「役割」を与えて指示を明確にする
AIに何かお願いする際、ただ質問するだけでなく「あなたは〇〇の専門家です」のように、AIに役割を与えると、より質の高い回答を得られるようになります。
例えば、「Web3について教えて」と聞くよりも、「あなたはWeb3に詳しいマーケターです。初心者にも分かりやすく、Web3のメリットを教えてください」と指示した方が、ペルソナ(読者)のニーズに合った、専門的でありながらも理解しやすい回答が得られます。
役割を与えることで、AIはどのような視点やトーンで回答すべきかを判断しやすくなるのです。
AIには情報過多・情報不足を避け、適切な情報量の見極める
AIへの指示は、情報が少なすぎても、多すぎても満足な結果を得られないことがあります。
情報が少ないと、AIは情報不足で満足な出力ができないことが多いです。
曖昧な質問では、AIが意図を汲み取れず、的外れな回答をしてしまう可能性があります。
一方で、指示が多すぎると、AIは情報過多ですべての指示を従いきれないときがあるため、伝えたいポイントがぼやけてしまうこともあります。
一番良いのは、伝えたいことを箇条書きにするなど、簡潔にまとめることです。
「矛盾した指示」はAIを混乱させる。具体的な指示の出し方
AIに指示を出す際には、矛盾した指示を避けることが重要です。
矛盾した指示を出すとその矛盾を解消させようと誤情報を出力することが多くなります。
たとえば、「〇〇については詳しく解説しないでください。ただし、〇〇のメリットは詳しく教えてください」といった矛盾した指示は、AIを混乱させ、結果的に不正確な情報につながることがあります。
そのため、指示は具体的かつシンプルにし、勘違いや指示の矛盾が生じないように事前の指示が必要です 。
AIの質問の仕方を変える応用テクニック
先ほども少し触れましたが、AIは質問の仕方を変えるだけで答えてくれなかった質問にも答えてくれることがあります。
たとえば、「タロットで占ってください」という抽象的な質問では、AIは「未来を予測できない」と答えるでしょう。
しかし、「プロのタロット占い師と同じプロセスでカードを選び、その結果選出されたカードの意味を教えてください」と聞くと、占ってくれることがあります。
これは、AIが「占い」という行為そのものではなく、「カードの意味を解説する」というタスクに焦点を当てることで、適切な回答を生成できるからです。
このように、制御しづらい行動をAIに行わせるときには、大枠の指示ではなくその行動や思考のプロセスを辿らせると、成功しやすくなります。
AIの精度を上げるための「ファクトチェック」の重要性
AIから得た情報が本当に正しいか、不安になることもあるでしょう。
そんなときは、出力結果を再度AIに真偽を確かめさせるのが有効です。
出力結果を全文コピーをし、再度AIにペーストしてから「この文章は正しいですか?」と真偽を確かめさせると、情報の精度が上がります。
このような行為をファクトチェックといいます。
ツールによっては、ファクトチェックをしてくださいと指示を出すだけで行ってくれるものもあります。
これは、AIが一度生成した情報を基に、より詳細な情報を探し出したり、論理的な矛盾がないかを確認したりするプロセスを促すために行います。
特に専門的な情報や、Web3のような新しい分野の情報については、ハルシネーションを回避するためにも、複数の情報源でファクトチェックを行うことが大切です。
Web3時代に役立つ!AIプロンプト活用シーン

Web3の専門用語をAIにわかりやすく解説させる方法
Web3の分野には、ブロックチェーンやNFT、DeFiなど、聞き慣れない専門用語がたくさんあります。
こうした用語を理解しようと、難解な解説記事を読んで挫折してしまった経験がある方も多いのではないでしょうか。
そんなときにAIを活用すれば、初心者にもわかりやすい言葉で解説させることができます。
「あなたはWeb3初心者に教える先生です。〇〇(専門用語)について、IT関係に詳しくない人でもわかるように、簡単な例えを使って説明してください」
たとえばこのように指示することで、専門知識がなくてもスムーズに学習を進めることができます。
AIを活用した効率的な情報収集術
Web3の最新情報は、Xのインフルエンサーやニュースサイトなど、さまざまな場所に散らばっています。
これらを一つずつチェックするのは大変ですよね。
そんなときもAIプロンプトが役立ちます。
例えば、「Web3の最新トレンドについて、主要なニュースサイトの記事を3つ要約して、それぞれの違いを教えてください」といった具体的な指示を出すことで、効率的に情報を収集し比較検討することができます。
AIに作業を任せて時間を創出することで、情報の海に溺れることなく、必要な情報だけをすくい上げることが可能になります。
ゲームやエンタメ分野でのAIプロンプト活用例
ゲーム好きの人にとって、AIは強力な味方になってくれます。
例えば、「(ゲームタイトル)の攻略法について、序盤でつまづきやすいポイントを3つ挙げて、初心者向けの解決策を教えてください」とAIに質問することで、効率よくゲームを進めることができます。
また、最近ではゲーム内のアイテムをNFTとして扱ったり、Play to Earn(遊んで稼ぐ)といったWeb3の概念を取り入れたゲームも増えています。
これらのゲームについてAIに質問する際も、プロンプトを工夫することで、より有益な情報を引き出すことができるでしょう。
まとめ:AIプロンプトをマスターしてWeb3時代を賢く生きよう!
この記事では、AIへの効果的な指示文である「プロンプト」の書き方について解説してきました。
AIは人間のように考えているわけではなく、次にくる単語を予測しているにすぎません。
だからこそ、私たちがAIにどのような指示を出すかが、その出力の質を大きく左右します。
「AIは嘘をつく」とよく言われますが、実は意図的なものではなく、「勘違い」や「指示の矛盾解消」から生まれていることが多いのです。
これを理解し、「役割を与える」、「情報過多や情報不足を避ける」、「矛盾のない具体的な指示を出す」といったコツを掴めば、あなたのAIはより優秀なパートナーとして応えてくれます。

あら、なるほど!AIが勘違いしてるだけって聞いたら、なんだか親近感が湧いてきたわ。これなら私にもできそうだわ!

ええ。まずは役割を与えたり、矛盾のないように質問してみると良いでしょう。小さな工夫で、AIとの対話はもっと楽しくなりますからね。
Web3時代において、AIを使いこなすスキルは、新しい情報を効率的に収集したり、複雑な概念を簡単に理解したりするための強力な武器となります。
この記事でご紹介したプロンプトのコツを参考に、ぜひあなたもAIとの対話を楽しみながら、Web3の波を乗りこなしていきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございます。
今回の記事はここまでとなります。
もしよろしければ、ほかの記事も読んでいただけると今後の活動に大変励みになります。
読んでいただいた皆様、応援してくださる方々、いつも本当にありがとうございます。
それではまた、別の記事でお会いしましょう。




コメント